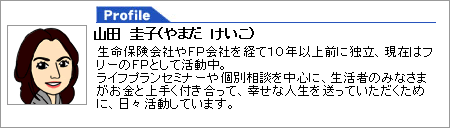■ 国民年金制度の歴史から今後の年金を考える
国民年金の始まりは、昭和34年(1959年)4月に制定された国民年金法で、これは自営業者や農林水産業者など、厚生年金保険等の被用者年金制度に加入していない者を対象とした年金でした。
そして、昭和36年(1961年)4月から、拠出制年金(保険料を納付することで年金が支給される制度)として国民年金の支給が開始しました。これにより、すべての国民が何らかの公的年金制度の対象となる国民皆年金の制度が実現しました。
この頃の国民の平均寿命は、昭和35年(1960年)で、男性65.32歳、女性70.19歳でした。老後といっても5年〜10年間ぐらいですから、年金の受給期間は短かったわけです。
その後、昭和48年(1973年)にオイルショックが起こり、高度経済成長が終わっていきました。この頃の平均寿命は、昭和45年(1970年)で、男性69.84歳、女性75.23歳に、昭和50年(1975年)では、男性71.79歳、女性77.01歳に伸びました。さらに出生率も低下していき急速な少子高齢化が進みました。そのことが公的年金制度に大きな影響を与えることが明らかとなり、制度の改正が必要となってきました。それでも老後期間は10〜17年間ぐらいですから、今よりはかなり短かったわけです。
このような社会変化の中で、昭和60年(1985年)公的年金制度の大改正が行われ、それまで各年金制度が独自に支給してきた基礎的な給付の部分を国民年金に統合し、現在のような全国民共通の基礎年金制度が始まりました。施行されたのは昭和61年(1986年)4月からです。
この頃の平均寿命は、昭和60年(1985年)で、男性74.95歳、女性80.75歳にまで伸びていました。国民年金法が制定された昭和34年頃に比べ、男女それぞれ10年程度寿命が延びており、老後期間も15〜20年間ぐらいまで長くなり、その分年金の受給期間も長くなっていきました。
その後、平成16年(2004年)の改正により、マクロ経済スライドによって年金の給付水準を調整する仕組みに変更されました。公的年金は世代間扶養の制度です。このまま少子高齢化が進めば現役世代の負担がどんどん重くなります。青天井に負担が増えることを防ぎ、収入の範囲内で給付を行うため、「現役世代の人数の変化」と「平均寿命の伸びに伴う給付費の増加」というマクロでみた給付と負担の変動に応じて給付水準を自動的に調整する仕組みのことです。
この頃の平均寿命は、平成17年(2005年)で、男性78.79歳、女性85.75歳となり、老後期間、年金の受給期間ともにさらに長くなっていきました。結果、公的年金だけに頼るのではなく、自分で老後のために資産形成をしていく必要があり、リタイアメントプランが重要とされるようになってきました。
下記の表のように、将来にわたって少子高齢化は進み、高齢者の人口割合はどんどん増え、2030年には1.7人の現役世代で1人の高齢者を支える時代になると推計されています。2060年には1.2人に1人ですから、かなり無理のある数値といえます。そろそろ年金を損得で考えるのはやめて、この制度がどうすれば社会保障として機能する形で存続していけるのか、国民も国と一緒に関心を持ち知恵を出していく必要がありますね。
【高齢者1人を支える現役世代の人数と平均寿命】
|
|
1990年
|
2010年
|
2030年
|
2060年
|
|
高齢者1人に対する現役世代の人数
|
5.1人
|
2.6人
|
1.7人(推計)
|
1.2人(推計)
|
|
平均寿命
|
男性76.04歳
女性82.07歳
|
男性79.59歳
女性86.35歳
|
男性81.88歳※
女性88.66歳※
|
2055年
男性83.67歳※
女性90.34歳※
|
※国立社会保障・人口問題研究所による死亡中位の仮定で標準的な将来生命表に基づいて推計
国民年金が始まった頃は、寿命も短く「厚く短く」でしたが、現在のように寿命が伸び、少子化も進み現役世代の人口割合が下がってしまったからには、「薄く長く」に変わっていくことは自然なことといえます。とは言え、公的年金の魅力は終身年金であることです。老後は、長生きリスクに備えた社会保障として薄く長く年金を受け取りつつ、無理なく働き続けることで薄く長く収入を得て、20〜30年間の老後期間を充実させていくことが普通になるのではないでしょうか。